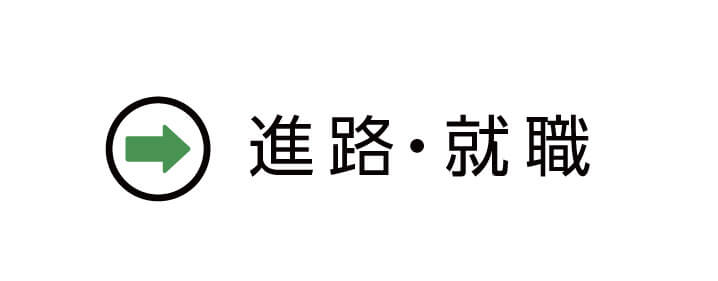「よりよい生き方を模索し、よりよい世界を築くための人文学」

人文学部長森川 慎也
北海学園大学人文学部は、人間と文化について学びたい人に開かれた学部です。人文学部では、言語、語学教育、文学、映画、思想、宗教、遺産、歴史、社会、自然、環境、メディア、テクノロジーなど、じつに多様な視点から人間と文化を考察することができます。
日常の外に出て、問題となる対象を見定める。少し距離を置いて観察し、自分なりに考えたことを発表したり文章にまとめたりする。そうすることで、自分の考察が他の人たちと共有できる共通の知になります。それには対象を観察する力、観察したことを言語化する力、口頭や文章で他人を説得する力が必要になります。
人文学部に限りませんが、大学で研究を行うには手順があります。最も重要な手続きはこれまでの知の集積に新たな知を付け加える行為だと言えるでしょう。新たな知を付け加えるには、当然、ある対象に関して蓄積されてきた知見を踏まえることが必要です。次のような状況を思い浮かべてください。見知らぬ人たちが集まって議論している場にみなさんが立ち会ったとします。まずは議論されている事柄や問題点や方向性を知ろうとしますね。そうすれば、より建設的な意見を述べやすくなります。
学問も同じで、ある事柄について誰がどのような意見をどのような方法で提示してきたのかをはじめに知ることが大切です。議論のなかで共有されてきた論点や課題を整理するために、先行する研究に目を通します。複数の意見をそれぞれ理解し、議論のどの部分が重要なのかを整理し、目の前の問題に対して自分なりの意見を提示するための準備を整えます。そうすれば問題を考察している他の人たちの議論に参加しやすくなります。
こうした手順を踏んで議論を深めていくこと――それが大学における学問の理想的なあり方です。この点は人文学も変わりません。しかし北海学園大学人文学部の強みは、多様な専門分野の教員がそれぞれの専門分野の知見を活かしながら、分野を超越したより大きな問題――たとえば、人間とは何か、人がよく生きるとはどういうことか、よりよい世界を構築するにはどうすればよいのか、といった問い――について議論を深めることができる点にあると私は考えています。こうした大きな問いは一朝一夕には答えが出ないかもしれません。考えるのに時間もかかります。皆が同じ結論に至るわけでもありません。ときには対立したり論戦したりすることさえあります。でも、それこそが人文学の良さです。頭ごなしに他人の意見を排除せずに、まずは耳を傾ける。そういう大らかさが人文学部にはあります。じっくり時間をかけて問題を吟味する。吟味・対話・議論のプロセスを大切にする。北海学園大学に入学された学生のみなさんには、こうした粘り強い議論に参加できるように知力を鍛えてもらいたいと思っています。人文学部で多くの視点やアプローチを身につけ、さまざまな角度から人間と文化について考え、自らの考えを発信し、多くの人と議論する場に参加してください。その先にきっと広い世界とつながる道筋が見えてくると思います。
人文学部の学生だからこそ、もうひとつ大事な問いかけをしてほしいと思います。それは、人間と文化を学ぶ「わたし」とは何か、人間全般ではなくこの「わたし」はどう生きるべきか、という問いかけです。人文学は、人間と文化を探究する学問ですが、同時に「わたし」というひとりの人間の生き方を模索するうえでも有益な視座を与えてくれます。人間の普遍的な特質、文化を含む人間の多様なあり方を学びながら、「わたし」の世界を広げ、よりよい生き方を模索しましょう。
人文学部の教員と学生は、ともに広く文化を学び、人間を探究し、よりよい世界を未来に築いていくことができます。明るい未来の構築に向けて、ぜひ一緒に古今東西の問題を吟味し議論しましょう。みなさんとの対話を楽しみにしています。
人文学部沿革
| 1993(平成5)年 | 北海学園大学人文学部1部日本文化学科,2部日本文化学科,1部英米文化学科,2部英米文化学科を開設 |
|---|---|
| 1999(平成11)年 | 北海学園大学大学院 文学研究科日本文化専攻修士課程を開設 |
| 2001(平成13)年 | 北海学園大学大学院 文学研究科日本文化専攻博士(後期)課程を開設 |
| 2003(平成15)年 | 北海学園大学大学院 文学研究科英米文化専攻修士課程を開設 |
| 2005(平成17)年 | 北海学園大学大学院 文学研究科英米文化専攻博士(後期)課程を開設 |